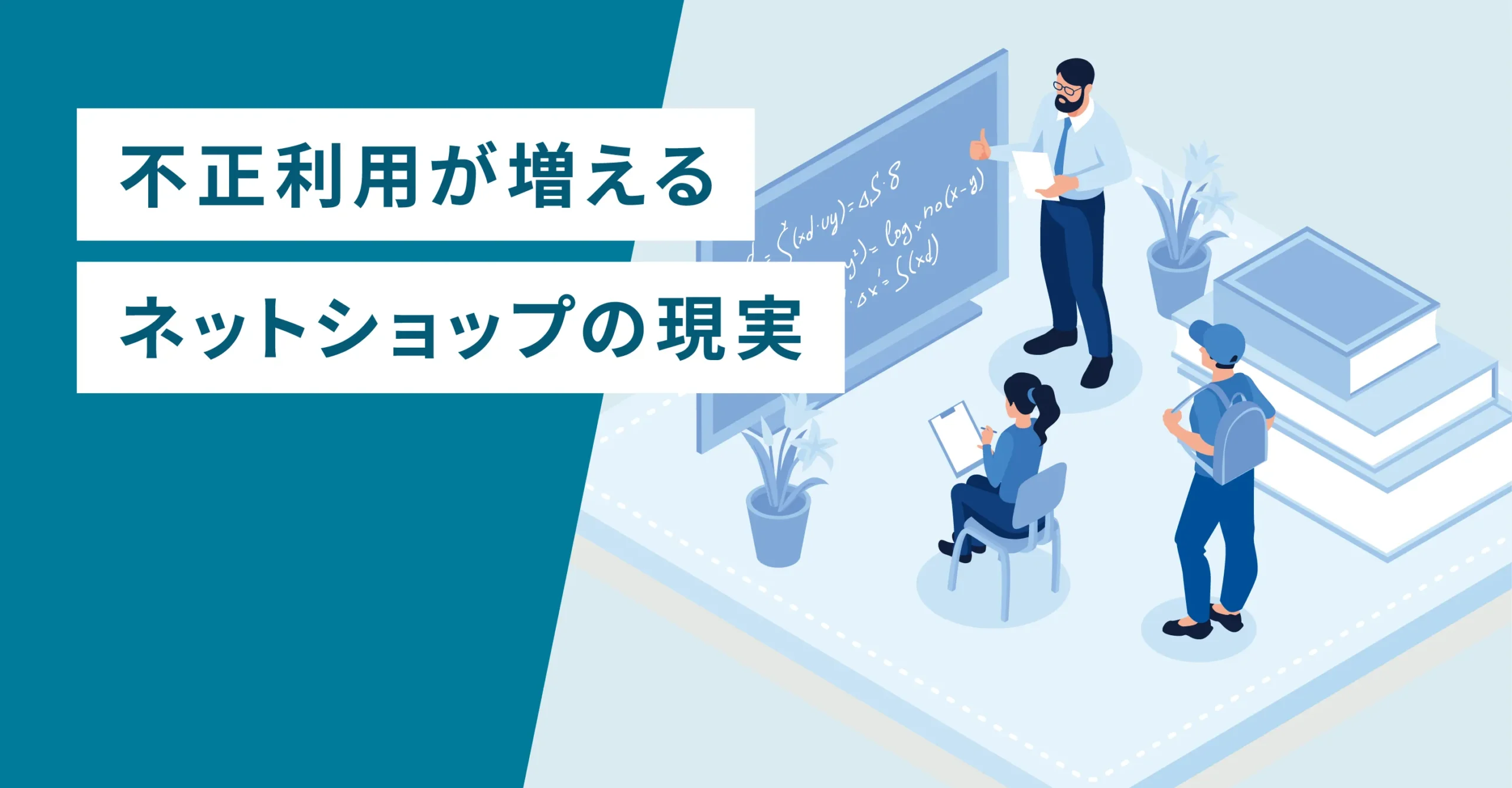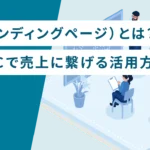ネットショップの不正利用は大手だけでなく小規模店も標的に
ネットショップを運営していると、思いがけないリスクに直面することがあります。
売上が伸びてきた矢先に増えてくるのが、「不正利用」と呼ばれるトラブルです。
クレジットカード番号の盗用や、後払いでの支払い逃れ、代引きの受け取り拒否など──被害の形はさまざまですが、共通しているのはショップ側が大きな損失を負うという点です。商品も売上も戻らず、顧客対応や再発防止に追われることになります。
しかも、こうした被害は大手だけではなく、小規模なショップや個人運営のネットショップでも決して珍しくありません。むしろセキュリティ体制が整っていない店舗ほど、狙われやすい傾向があります。
本記事では、なぜ不正利用が増えているのか、どんなジャンルが特に狙われやすいのか、そして事業者がどのように対策を取るべきかを、わかりやすく解説していきます。
「不正注文/不正利用」とは何か
ネットショップにおける「不正注文」や「不正利用」とは、本来の購入意思を持たない第三者による注文行為を指します。代表的なのは、盗まれたクレジットカード番号を使った「なりすまし注文」です。
こうした注文は、一見すると通常の購入と変わりません。決済は通り、ショップ側も発送を進めてしまいます。しかし後日、カード会社から「この取引は不正利用だった」と通知されれば、売上はチャージバック(取り消し)され、商品も戻らないまま損失となります。つまり、ショップ側が被害をすべて負担するのです。
クレジットカード以外でも、不正は発生します。
- 後払い決済の不払い:架空の住所や本人ではない情報で注文し、商品だけを受け取って支払いをしないケース
- 代引きの受取拒否:商品は発送済みなのに受け取りを拒否され、送料や手数料だけが店舗の負担になるケース
- いたずら注文・大量注文:明らかに購入意思がないのにカートに入れられ、在庫を押さえられてしまうケース
いずれも、ショップの売上や在庫、配送コストに直接ダメージを与える行為です。しかも、規模や業種を問わず発生するため、「自分の店は小さいから大丈夫」とは言い切れません。
こうした背景から、不正利用は「単なるトラブル」ではなく、ネットショップ運営における避けて通れないリスクとして認識する必要があります。
最新データで見る不正利用の実態
ネットショップにおける被害額の推移を追うと、その深刻さは年々増しており、すでに業界全体の課題として無視できない規模にまで拡大しています。ここでは、直近の統計データをもとに、いま起きている不正利用の実態を見ていきましょう。
被害額は年々拡大
日本クレジット協会の調査によると、クレジットカード不正利用による被害額は2024年に555.0億円となり、前年から2.6%増加しました。2023年の被害額は540.9億円であり、過去数年間にわたり高止まりが続いている状況です。
出典:日本クレジット協会 2025年3月7日発表
わずか10年前の被害額は300億円台でしたが、EC市場の拡大とともに被害規模も膨らみ、現在はその倍近い金額に達しています。つまり、ネットショップの普及と比例するように、不正利用のリスクも増大しているのです。
手口の主流は「番号盗用」
被害の内訳をみると、カード番号盗用が93.3%を占めるまでに拡大しており、偽造カードによる被害はわずか0.6%にとどまっています。
出典:内閣府 2023年時点 消費者委員会資料
これは、カード番号や有効期限・セキュリティコードなどの情報が流出・売買され、ネットショップなどの非対面決済で不正利用されるケースが主流になっていることを示しています。
事業者の対応状況
一方で、事業者の対策状況を見ると課題が残ります。かっこ社が2022年に実施した調査では、EC関連企業550社のうち77.5%が不正対策を実施している一方で、19.1%の企業は「未実施」と回答しています。
出典:かっこ株式会社調査 2025年6月更新
つまり、全体の約5社に1社は何の対策も取っておらず、そのような店舗が狙われやすい「穴」となっている可能性が高いのです。
ネットショップが狙われる理由
不正利用の被害額や手口の推移を見てきましたが、ではなぜネットショップはこれほど狙われやすいのでしょうか。理由は、商品特性・店舗の規模・販売手法・決済手段など、複数の要因が絡み合っています。ここでは特に多くの事例で共通して見られる「狙われやすさの要因」を整理してみましょう。
換金性が高く、短期間で現金化できる商品
不正利用者にとって最も重要なのは「いかに早く現金化できるか」です。ブランドバッグや高級時計、最新のゲーム機や家電といった商品は、フリマアプリや中古市場を通じて短期間で売却可能です。そのため、こうしたジャンルは不正注文が集中する傾向にあります。
さらに近年はコスメや健康食品など、単価は比較的低くても需要が安定している商材も狙われています。理由は、少量でも出品すればすぐに買い手がつくため、安定的な換金ルートになるからです。
ショップ規模や認証制度に関係なく狙われる
「大手のECサイトは狙われやすいが、小規模店は安全」と思われがちですが、実際には逆のケースも少なくありません。不正利用者は“突破できる場所”を探しているため、セキュリティ体制が手薄な小規模ショップや個人運営の店舗は、むしろ標的になります。
また、3Dセキュアなどの認証制度を導入していても、その設定が不十分だったり、後払い・代引きといった別の決済手段には適用されない場合もあります。つまり「認証制度がある=安全」ではなく、不正利用者は常に“抜け道”を探しているのです。
したがって「規模や認証制度に関係なく狙われる」とは、大手・小規模を問わず、不正利用者にとって弱点があれば攻撃対象になるという意味合いなのです。
初回限定・数量限定・キャンペーン商品
初回限定セットや数量限定キャンペーン商品は、複数アカウントを使った注文や架空名義での大量購入に狙われやすい典型です。人気商品を不正に仕入れて転売すれば大きな利益を得られるため、犯罪者にとって格好の標的となります。特に短期間のキャンペーンではショップ側も確認作業が追いつかず、リスクが高まります。
支払い手段の特性
不正利用のリスクは、選ばれる支払い手段にも大きく左右されます。
- クレジットカード:番号盗用による「なりすまし」が主流。不正が発覚するとチャージバックで売上が取り消され、商品も戻りません。
- 後払い決済:虚偽の住所や本人以外の名義で注文され、代金が回収できないケースが多発します。
- 代引き決済:商品発送後に受取拒否されると、送料・手数料がすべてショップの負担になります。
つまり、支払い手段ごとに特有のリスクがあり、どの決済方法を提供するかも不正利用のリスク管理に直結するのです。
被害が多い商材とは
ネットショップにおける不正利用の被害は、すべての商品ジャンルで起こり得ますが、特に集中して狙われる商材があります。価格が高い、需要が高い、転売しやすい──そうした特徴を持つ商品は、不正注文のリスクが高くなります。自分のショップが扱う商材がこのリストに含まれていないか、確認しておくことが大切です。
被害が多い商材とその特徴
| 商材 | 被害が多い理由 |
|---|---|
| ブランド品・ファッション小物 | 高い価値を持ち、転売市場で人気がある。模造品混入やブランドロゴの無断使用など別の法的リスクとも絡む。ブランド品は一度不正に手に入ると、再販が容易なケースが多いため狙われやすい。 |
| 家電・AV機器・PC周辺機器 | 高価格帯であり、部品単位での需要もある。最新モデル・人気モデルは在庫の回転が速く、転売差益が取りやすい。 |
| ゲーム機・ゲームソフト | 発売直後の需要が非常に高く、限定性や希少価値がつくことが多いため、予約や初回販売時などに不正注文が発生しやすい。ゲーム機器は「入手後に中古での再売が容易」という点で狙われやすいです。 |
| チケット・イベント券 | 使用日が限定されていて価値が明確。転売価値が高いため、偽名・転売目的での購入が繰り返される。追跡や返却が困難なケースもあり、被害の損失率が高い。 |
| コスメ・健康食品 | 比較的低価格でもブランド力や需要が大きく、消費者が継続購入することが多いため、転売目的・不正注文目的でターゲットになる。 |
法・ガイドラインについて
不正利用はもはや「起きたら困るトラブル」ではなく、国のガイドラインで対策が義務づけられている段階に入っています。ネットショップを運営する事業者にとっては、制度面で必ず対応すべきことと、実務の工夫でリスクを減らすことを切り分けて考える必要があります。
ガイドラインに沿った3Dセキュア2.0の導入
経済産業省とカード業界が定める「クレジットカード・セキュリティガイドライン」では、2025年3月末までに全てのEC加盟店で3Dセキュア2.0を導入することが求められています。従来のパスワード方式に代わり、端末や購入履歴をもとにリスクを判定する仕組みを採用し、低リスクの取引はスムーズに処理できるのが特徴です。つまり、不正利用を防ぎつつ顧客体験を損なわない“両立策”として必須化されているのです。
▼関連記事
クレジットカード不正利用が過去最大に!3Dセキュア2.0の導入義務化?
高額注文・転送会社宛などのリスク条件を運用ルール化
制度的な対策だけでは不十分です。不正利用はシステムをすり抜ける形でも発生します。特に、高額注文が短時間に集中したり、転送会社宛の住所に配送が指定されたりする場合は要注意です。こうした典型的なサインを「運用ルール」として明文化し、社内で共有することが欠かせません。
不正検知システムやカート標準機能の活用で人的負担を軽減
加えて、不正利用は人力で全てをチェックしようとすれば運営者の負担が大きくなります。そのため、不正検知システムやカートに標準搭載されている機能を積極的に活用し、怪しい注文を自動でフラグ付けできる体制を作ることが重要です。人的な確認作業は「最終確認」にとどめることで、限られたリソースでも効率的に被害を減らせます。
EC事業者が取れる具体的な対策
制度やシステムによる防御は不可欠ですが、それだけで不正利用を完全に防げるわけではありません。現場の運営でどんなルールを設け、どんな対応を心がけるかが被害を最小限に抑えるカギとなります。ここでは、日々のネットショップ運営で取り入れやすい具体的な工夫を紹介します。
怪しい注文を見抜く視点を持つ
不正利用は一見すると普通の注文に見えるため、最初から完璧に判別することは困難です。ただし、典型的な“赤信号”があります。たとえば深夜に立て続けに高額商品が注文される、同じ住所に名義だけが違う注文が繰り返される、転送会社の住所が指定される──これらは不正注文で頻繁に見られるパターンです。こうした兆候を意識して日々の注文を確認するだけでも、不正を早期に察知できる可能性が高まります。
本人確認をルール化する
怪しいと感じた注文をそのまま出荷してしまうと、被害は取り戻せません。そこで重要になるのが、本人確認をルール化することです。高額商品の場合や初めて利用する顧客の場合は、電話やメールで「ご注文に間違いがないか」を確認する一手間を加えるだけでも効果は大きいでしょう。また、不審な場合は支払い方法の変更をお願いするなど、事前に対応フローを決めておけば担当者が迷わずに行動できます。
支払い手段ごとの工夫を加える
決済方法によって不正利用のリスクは異なります。後払いであれば初回購入者には上限額を設ける、代引きであれば初回は利用不可にするか事前連絡を必須にする、クレジットカードなら承認プロセスを強化する──といったように、支払い手段ごとに最低限の工夫を加えておくことで被害の広がりを防ぐことができます。
記録を残し、社内で共有する
不正注文のパターンは繰り返されることが多いため、記録を残すことが重要です。怪しい注文や実際に被害にあったケースは「不正注文リスト」として社内で共有しておくと、次回以降の判断が格段にスムーズになります。リストが蓄積されれば、自社ならではの不正利用の傾向が見えてきて、より効果的な対策につながります。
誤解しがちな考え方
不正利用対策については、EC事業者のあいだでよく誤解されがちなポイントがあります。正しい理解がないままでは「大丈夫だろう」と油断してしまい、かえって被害を招きやすくなります。ここでは代表的な二つの誤解を取り上げてみましょう。
「3Dセキュアを導入すれば不正利用にあわない?」
3Dセキュア2.0は、クレジットカードの番号盗用による不正利用を防ぐ上で非常に効果的です。しかし、万能ではありません。たとえば、後払い決済での支払い逃れや代引きの受取拒否、いたずら目的の大量注文といったケースは、3Dセキュアの導入だけでは防ぐことができません。
つまり「3Dセキュア=すべての不正利用対策」ではなく、「カード不正利用を大幅に減らすための強力な手段のひとつ」として位置づけるのが正解です。
「小規模店は狙われない?」
「うちは小さなショップだから、不正利用のターゲットにはならないはず」と考える事業者は少なくありません。しかし実際には、小規模店こそ狙われやすい傾向があります。大手ECは不正検知システムや監視体制を整えているため、不正者にとってリスクが高いのです。逆に、セキュリティが手薄で監視も不十分な小規模ショップは「穴場」とみなされ、狙われやすくなります。
「不正利用はカード会社が補償してくれるから大丈夫」
クレジットカード会社には利用者を守る補償制度がありますが、その一方で店舗側には「チャージバック」という仕組みがあり、売上が取り消されてしまう場合があります。つまり、消費者の安心は制度として整っている一方で、店舗にとってはリスクが残るのです。だからこそ、事前に不正を防ぐ仕組みづくりが重要になります。
「怪しい注文は目視で見れば防げる」
一件ごとに丁寧に確認すれば不正は防げそうに思えますが、実際には件数の多さや手口の巧妙さにより、人の目だけでは限界があります。さらに誤って正規の注文を止めてしまう「誤検知」のリスクもあり、売上機会を逃してしまう可能性もあります。
「一度対策を導入すれば安心」
不正利用の手口は常に変化しています。数年前には主流だった偽造カード被害はほとんど消え、現在は番号盗用が9割以上を占めています(内閣府 2023年時点 消費者委員会資料より)。つまり、導入時点の対策がいつまでも有効とは限らないのです。定期的な見直しが欠かせません。
「うちの商品は安いから狙われない」
ブランド品や高額商品だけが危険と思っている人もいますが、実際にはコスメや健康食品など単価が低くても需要が高い商品も狙われています。少額でも繰り返し仕入れて転売すれば、犯罪者にとって十分利益になるからです。
不正利用への理解には、思い込みや誤解がつきものです。
3Dセキュアを導入すればすべて解決するわけではなく、小規模ショップであっても狙われる可能性は十分にあります。さらに、補償制度は消費者を守る仕組みであっても、店舗にとってはリスクが残り続ける点も忘れてはいけません。
大切なのは、「うちは大丈夫」と思い込まないこと。手口は常に変化し、狙われる商材も広がっています。だからこそ、正しい知識を持ち、仕組みと運用の両面で備えていくことが、被害を防ぐ最初の一歩になるのです。
まとめ
ネットショップを取り巻く不正利用のリスクは、年々高まっています。被害額の増加、番号盗用の急増、小規模店にまで広がる被害──どれも「自分には関係ない」とは言えない現実です。
しかし、正しい知識を持ち、ガイドラインに沿った制度対応と、現場での運用ルールを組み合わせることで、被害は大幅に減らすことができます。不正利用対策は「コスト」ではなく、「お客様に安心して買っていただくための投資」であり、信頼を守る第一歩なのです。
そして、こうした仕組みをゼロから自力で整えるのは容易ではありません。Eストアーショップサーブなら、3Dセキュア2.0対応や不正注文検知機能が標準で備わっており、店舗側の負担を減らしながらセキュリティを高めることができます。不正利用のリスクを抑えつつ、日々の運営に集中できる環境を整えることが可能です。
不正利用から店舗を守りたいとお悩みを抱えている方は、ぜひ Eストアーショップサーブのお問い合わせフォーム からご相談ください。安心と信頼を支える仕組みづくりを、ネットショップ構築システムを提供している私たちがサポートいたします。