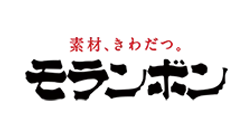食を通じた豊かな暮らしを支える存在に

1972年に焼肉店からスタートし、創業から50年以上の歴史を重ねるモランボン株式会社。看板商品である「ジャン 焼肉の生だれ」をはじめ、韓国の伝統食品メーカーとの共同開発商品など、日本の食卓に韓国料理を提案し続けています。
今回は、企業理念に基づいた商品開発やお客様との関わり方について、開発本部 ・コミュニケーション開発部の藤田様にお話を伺いました。
たった一言から始まった「ジャン」の軌跡
お客様の要望から誕生した看板商品「ジャン 焼肉の生だれ」
成り立ちについて
藤田様:最初は焼肉店の経営からスタートしました。お客様から「焼肉のたれが美味しいから分けてほしい」というご要望をいただいたことがきっかけで、7年の歳月をかけて誕生したのが、焼肉のたれ「ジャン」です。モランボンと言えば「ジャン」という商品で、社員の中でも強く意識される看板商品となっています。
焼肉店から始まった事業は、看板商品「ジャン」の誕生を機に調味料の製造・販売へと展開しました。以来、韓国料理に関連する商品ラインナップを拡充し続けています。またその専門性を活かし、現在では地元府中で焼肉をメインで提供するモランボン本店の他、韓国料理を中心とした居酒屋も3店舗展開するなど、製造・販売だけでなく外食事業も手がけています。
素材本来の風味にこだわった一度も加熱しない製法
「ジャン」の特徴について

藤田様:「ジャン」の最大の特徴は、生ブレンド製法です。原料を調合した後、一度も加熱をしないため、薬味や香辛料の風味が格別です。また、厳選素材だけを使用している点も特徴で、薬味・香辛料・果汁など13種類の厳選素材のみをブレンドしています。
「ジャン」は要冷蔵商品のため、製造工場から販売先まで一貫して10℃以下での冷蔵管理を行うことで、おいしさを保っています。発売当時は賞味期限が7日間と非常に短く、「買ってすぐに使ってください」と案内して販売していました。当時はお肉屋さんに多大なご協力をいただきながら販売を行っていましたね。その後、徐々に改良を重ね、現在は賞味期間を90日まで延ばすことができています。46周年を迎えた今でも、生ブレンド製法にこだわり、素材本来の風味を大切にしています。
「ジャン」以外にも、モランボンが韓国伝統食品ブランドYANGBANと共同開発した「韓キムチ」は15周年、韓国調味料や春雨などがセットになった「韓の食菜シリーズ」が20周年を迎えました。
「韓の食菜シリーズ」は、チャプチェ・春雨プルコギ・ビビンパ・チヂミなどの種類があり、人気の韓国メニューがおうちで簡単に作れる韓国調味料商品として、ご好評いただいています。これらの商品を通じて、日本の食卓に韓国料理を提案し続けています。

想いが紡ぐモランボン愛
コミュニケーションツールとなるレシピの提案
レシピの発信について
藤田様:お客様の実際のニーズに応えるレシピ開発を心がけています。例えば「餃子の皮の使い方」や「すき焼のアレンジメニュー」など、食材の活用方法を提案するレシピは、コーポレートサイトでもよく閲覧されているコンテンツです。レシピは営業プロモーション部門が7割、商品開発部門が2割、コミュニケーション課が1割程度の割合で作成しており、それぞれの視点を活かした提案ができるよう工夫しています。
長年愛してくださっているお客様の存在が励みになる
印象に残っていること
藤田様:SNSなどを見ていると、私たち以上にモランボンを愛してくださっているお客様が数多くいらっしゃることに気付かされます。具体的な例として、最近では『コク旨スープがからむ 魅惑の丸鶏清湯(ちんたん)鍋用スープ』がECサイトで好調な売れ行きを見せているんです。この商品は10パック入りとなっており、一般のお客様にとってはハードルが高い販売形態ですが、スーパーでの取り扱いが終了した後もECサイトで継続的にご購入いただいています。
長年商品を使い続けていただいているお客様の思い入れの深さは、私たちにとって何より大きな励みとなっているんです。
お客様相談室に届くお客様の声は、毎週社内で共有させていただいています。特に商品に関するご意見やご要望については、今後の改善につなげられるよう、関係部署と連携を取りながら対応しています。
お客様の投稿から共感の輪が広がり商品の人気が高まる
SNSで話題になった商品について
藤田様:最近Xで「モランボンさんのこれ美味しい」という投稿から『BISTRO FISH ムニエルの素』が話題になりました。店舗での取り扱いが少なかったこともあり、ECサイトでの購入が増加したんです。
この商品の場合は「使ってみたら美味しくできた」という実体験の投稿がきっかけとなり、「こんな商品があるんだ」「ちょうどサーモンの季節だから私も使ってみよう」といった形で、SNSならではの共感の輪が広がっていきました。

「薬食同源」の精神から生まれる食育活動
食べることが健康につながる商品展開で食の豊かさに貢献する
取り組みについて
藤田様:私たちは「多様な食文化の交流・融合から新しい価値を創造し、食の豊かさに貢献する」ことを理念として掲げています。その中で、食べることで健康になれる「薬食同源」の考えを大切にしてきました。この考えは創業時からの精神として根付いており、その発展形として「Well-Being Vegelife (ウェルビンベジライフ)」というブランドを立ち上げ、野菜を取り入れた健康的な食生活を提案する商品展開となっています。
食事を通してより豊かな暮らしを提案する取り組みとして、フードバンク活動や手づくり餃子教室を通じた食育など、SDGsに関する活動も多く行っています。
昨年からはSDGsのページを開設し、これらの活動の発信も始めました。ただ、社内ではまだまだ多くの取り組みがあるので、今後はそれらも積極的に発信していきたいと考えています。
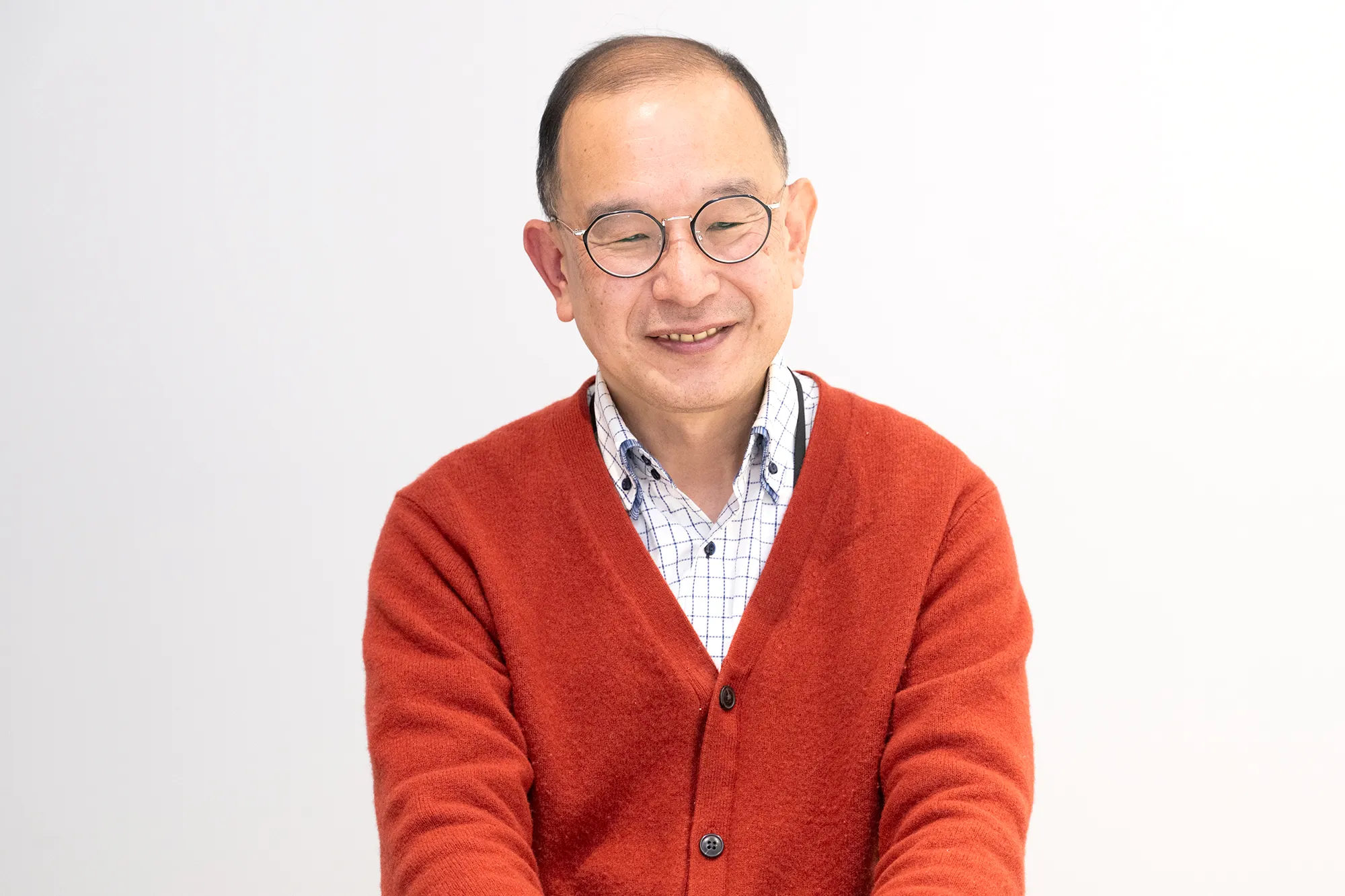
食材選びから考える、「食」の大切さを学ぶ餃子教室
食育活動について
藤田様:食育活動の一環として、手づくり餃子教室を定期的に開催しています。特徴的なのは、調理するだけでなく買い物から始めることです。ほかにも、食材の選び方や地産地消の考え方なども含めてお伝えしているんです。単に料理を作るだけでなく、食の大切さを総合的に学んでいただける場として位置付けています。餃子教室は本社ビルやスーパーマーケットなど、様々な形式で開催しています。本社ビルでの開催時は、親子で15〜16人程度の規模で、講師4名体制で実施しています。対象は小学1年生から6年生までのお子様です。
餃子づくりは包む工程が難しいため、講師がしっかりサポートできるよう、少人数制にしています。小学1年生のお子様は餃子を包むのに苦戦することもありますが、一口餃子なら簡単に包めるなど、年齢に応じた工夫もしています。
自分で包んだ餃子を自分で焼いて食べるという体験は、お子様に大変好評で「このような機会は大事」「とても楽しかった」という声を多くいただいています。応募も多く、「また参加したい」というリピーターの方も増えています。
お客様が求めるものを追求し続ける使命感
当社が掲げる「真にお客様が求めるものを見極め、安全・健康、そしておいしさで独創性を追求し続けること」、これが私たちの目指す姿です。また、「社会と調和し、環境と共生する企業であること」を重視し、「個を尊重したチームワークとスピードをもって変化に挑戦し続ける組織作り」を進めています。これらの理念と目指す姿のもと、これからも食を通じて、お客様の豊かな暮らしに貢献していきたいと考えています。