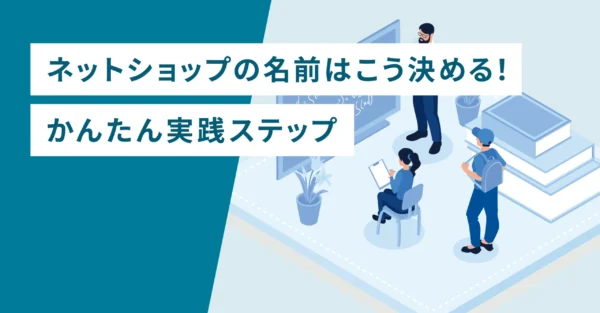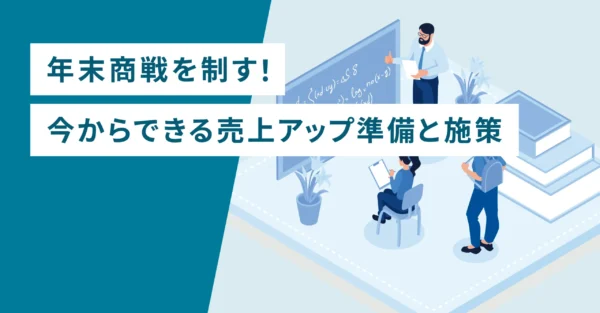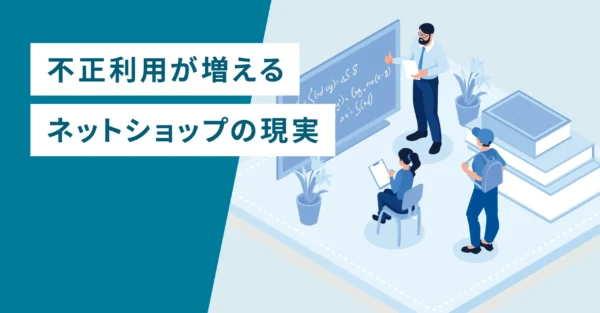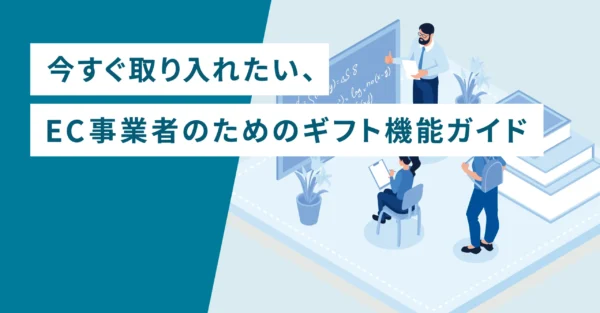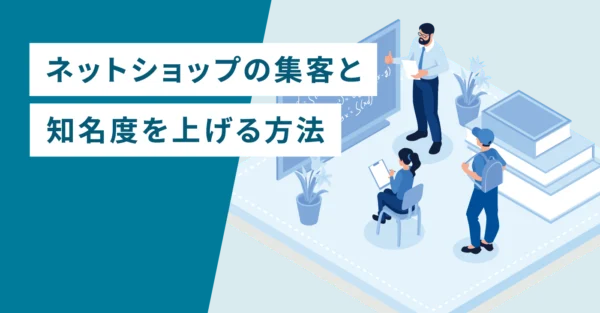カゴ落ちを防げば売上が変わる!原因と今すぐできる改善術
公開日:2025.11.13
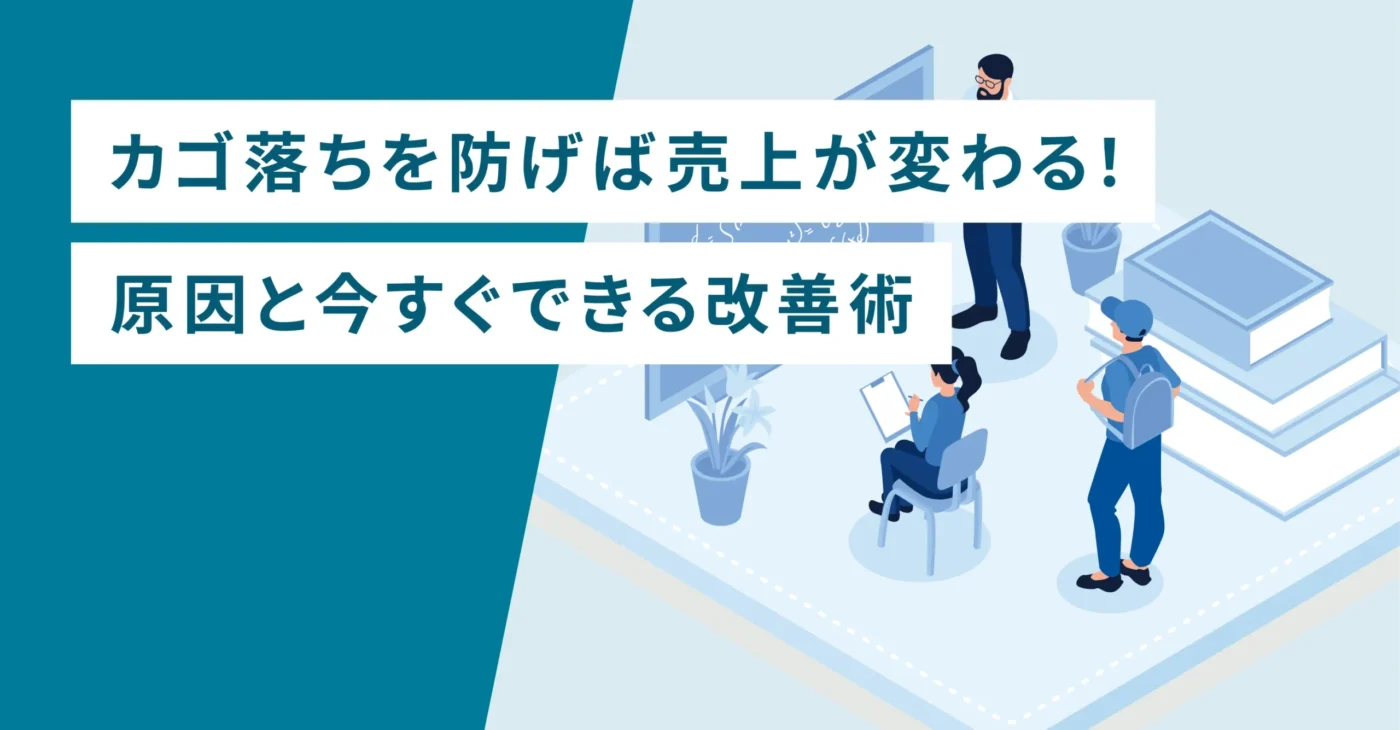
カゴ落ちの原因と改善策をわかりやすく解説します
商品をカートに入れたのに、購入されない「カゴ落ち」。
ネットショップを運営していると、多くの人がこの現象に悩まされます。
FORCE-R株式会社の調査(2024年12月)によると、カゴ落ちの主な理由は「送料や手数料が高かった(46.1%)」「後日購入しようと思った(29.8%)」「他の商品を見ている間に忘れた(26.9%)」でした。
出典:FORCE-R株式会社による「カゴ落ちの主な理由」調査(2024年12月)
つまり、購入意欲そのものが消えたのではなく、ちょっとした心理や不便さで“やめてしまった”ケースが多いのです。
カゴ落ちは珍しいことではありませんが、原因と対策によって売上を改善できます。この記事では、顧客心理や統計データを踏まえつつ、具体的な改善のヒントをわかりやすく紹介します。

カゴ落ちとは?売上が消えてしまう瞬間
「カゴ落ち」とは、ネットショップでお客様が商品をカートに入れたのに、購入を完了せずに離脱してしまうことを指します。
イメージしやすい例を挙げると、コンビニでお菓子を手に取りレジに並んだのに、「やっぱりやめよう」と棚に戻すようなものです。実店舗では多少珍しいかもしれませんが、ネットショップではむしろ日常的に起きています。
なぜなら、オンラインショッピングは「気軽に試す」ことができる環境だからです。購入意欲が低い段階でもカートに入れ、条件や気分次第で購入をやめる行動は珍しくありません。重要なのは、この「売上が消えてしまう瞬間」が想像以上に多いという事実です。
お客様が購入をやめてしまう理由
カゴ落ちの理由は一つではなく、顧客心理やサイト環境が複雑に絡み合っています。以下では代表的な5つの理由を見ていきましょう。
予想外の費用にためらう
最も多い理由は「思ったより費用がかかった」というものです。商品ページを見た時点では「この価格ならお得だ」と感じていても、購入手続きの途中で送料や手数料が加算されると、一気に「損をした気分」へと変わってしまいます。これは行動経済学でいう「損失回避性」の心理が強く働く場面です。
手続きが面倒で離脱する
長い入力フォームや会員登録の必須化は、ストレス要因です。「面倒だな」と思った瞬間にタブを閉じてしまう人は少なくありません。店舗で言えば、レジ待ちの列が長すぎて買うのをやめる心理と似ています。
比較・検討の途中で忘れてしまう
「一度カートに入れておけば安心」と思い、他の商品や他サイトを見比べているうちに忘れてしまうケースです。強い購買意欲があっても「今は買わなくてもいいか」と後回しにし、そのまま購入されないこともあります。
決済・配送に不安を感じる
「希望する決済方法がない」「配送日がいつなのか不明」「返品できるか分からない」など、不安が残ると購入完了まで進めません。特に初めて利用するショップではこの不安が強く働きます。
サイトや操作性に不便を感じる
スマホで入力がしづらい、動作が重い、途中でエラーになるなど、サイト自体の不便さも離脱要因です。オンライン購入は「スムーズに買えるか」が重要であり、ストレスを感じた瞬間に顧客は離れてしまいます。
売上や顧客体験に影響するカゴ落ち
カゴ落ちは放置すると、売上に直結する大きな課題になります。
実際に各種調査でも、平均的なカゴ落ち率は60〜70%前後という結果が報告されています。つまり、10人中6〜7人は「カートに入れたのに購入しない」という行動をとっていることになります。
これは単に「売上を逃す」だけでなく、顧客体験そのものにも影響します。
「買おうとしたのに不便で諦めた」という経験は、サイトへの再訪率やリピート購入意欲を下げてしまうからです。結果的に、機会損失と顧客離れの両方を招いてしまいます。
出典:株式会社イー・エージェンシー「CART RECOVERY導入552サイトにおけるカゴ落ち率調査(2024年1月〜12月)」
出典:Baymard Institute「Cart Abandonment Rate – Latest Research」(世界49調査の平均値 70.19%)
カゴ落ち率はどれくらい?数字で見る現実
海外のBaymard Instituteの調査では、世界平均のカゴ落ち率は約70%とされています。日本国内でも大きな差はなく、60〜80%程度が一般的です。
出典:Baymard Institute「Cart Abandonment Rate – Latest Research」
特にスマホでの購入は離脱率が高い傾向があります。入力の手間や操作性の悪さが影響しており、モバイル最適化の重要性が浮き彫りになっています。
例えば月商100万円のショップでカゴ落ち率が70%だと仮定すると、本来は約300万円以上の売上機会が眠っている計算になります。小さな改善でこの一部を取り戻せるなら、売上に与えるインパクトは大きいのです。
カゴ落ちを減らす改善策
ここからは、実際にカゴ落ちを減らすための具体的な改善策を紹介します。ポイントは「なぜ有効なのか」と「どう実践するのか」をセットで考えることです。
1. 送料・手数料の表示方法の工夫
購入途中で初めて送料が加算されると、顧客は「裏切られた感覚」を持ちます。商品ページやカート画面で早い段階から総額を示すことで、不安を払拭できます。送料無料ラインの設定やまとめ買い割引も効果的です。
2. 購入フローの簡略化(フォーム最適化・ゲスト購入)
入力項目を極力減らし、必要最低限の情報だけに絞ると離脱率は下がります。会員登録を必須にせず、ゲスト購入を導入することも大切です。
3. 多様な決済方法の導入(クレカ・コンビニ・スマホ決済)
希望する決済方法がないと、それだけで購入を諦める顧客もいます。クレジットカードはもちろん、コンビニ払い、PayPayや楽天ペイなどのスマホ決済を用意することで購買機会を逃さなくなります。
4. 配送・返品ポリシーの提示
「いつ届くか」「返品できるか」が分からないと不安になるため、商品ページに配送目安や返品ポリシーを明示するだけで、購入完了率は上がります。
5. カゴ落ちメールやLINEによるリマインド施策
「カートに商品が残っています」という通知は有効です。メールやLINEでリマインドすることで、一定数のお客様が購入に戻ってくることがわかっています。特に1通目の送信や、クーポンを添えた施策は効果的とされており、売上の回収につながりやすい手法です。
カゴ落ちメールで“忘れられた購入意欲”を呼び戻す
お客様がカート内に商品を入れたまま離脱してしまう「カゴ落ち」。これは、”購入の意思はあったけれど、ちょっとしたことがきっかけで離れてしまった”状態です。しかし、離れてしまったからといって、その意思まで消えてしまったわけではありません。そこで有効なのが、「カゴ落ちメール」というリマインド施策です。
実際にEストアーショップサーブ導入店舗では、カゴ落ちメール施策により売上が全体で平均2%、最大5%向上したという結果も出ています。
▼関連記事
カゴ落ちメールをやらない理由はない!
さらに、メールの「件名」やタイミングを工夫して取り組んだ事例もあり、店舗の声から学べるヒントが豊富です。
▼関連記事
件名で効果が変わる!カゴ落ちメールの成功事例
まとめ
カゴ落ちはネットショップでは避けられない現象です。しかし重要なのは「なぜ離脱したのか」を理解し、改善に取り組むこと。送料の見せ方、購入手続き、決済方法、配送の安心感、リマインド施策、サイトの快適さ――いずれも小さな工夫で成果が変わります。
一つの改善が、売上を大きく動かすきっかけになります。
まずは自分のショップの購入フローを見直してみませんか?
そして、もし「どこから手を付ければいいか分からない」と感じたら、Eストアーショップサーブ を活用するのも一つの手です。豊富な決済手段やカゴ落ち対策の仕組みが揃っており、運営を始めたばかりのショップでも安心して改善に取り組めます。
カゴ落ち対策から売上改善まで、まずはお気軽にEストアーショップサーブへお問い合わせください。