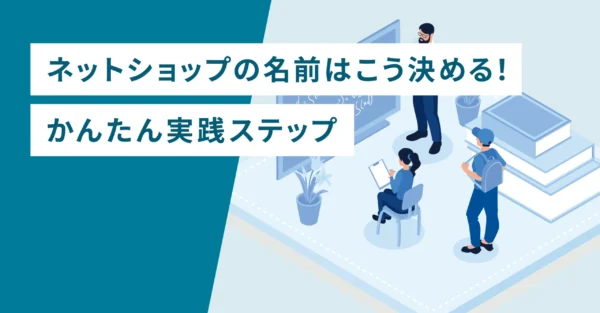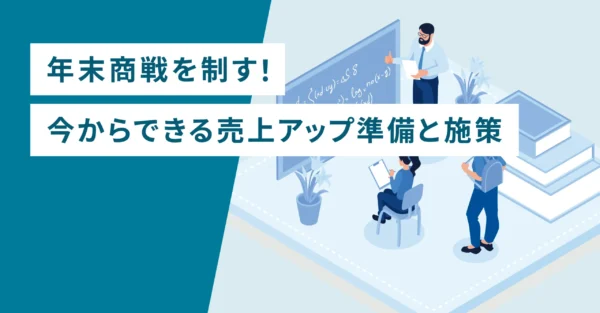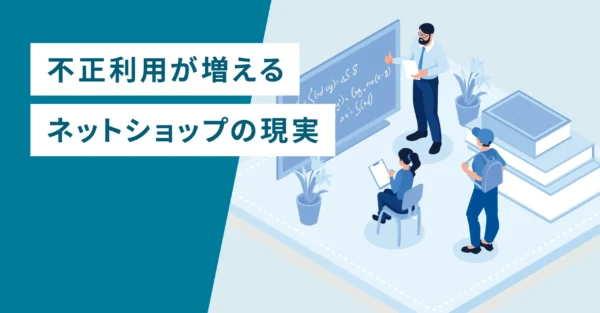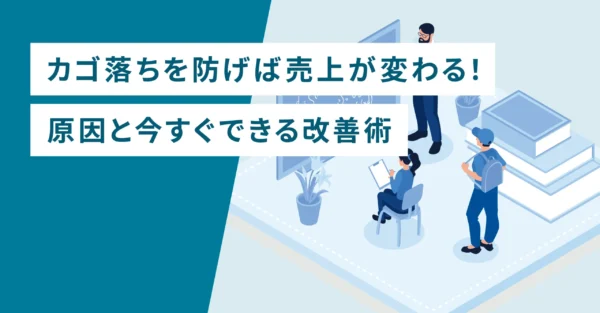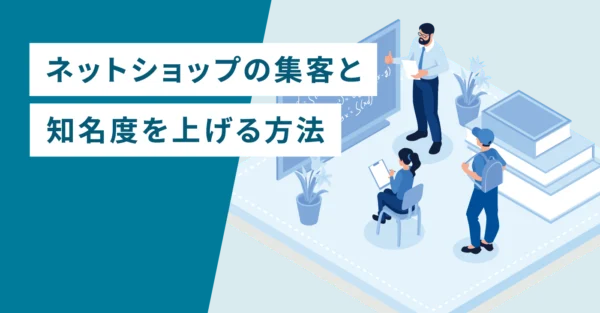今すぐ取り入れたい、EC事業者のためのギフト機能ガイド
公開日:2025.11.04
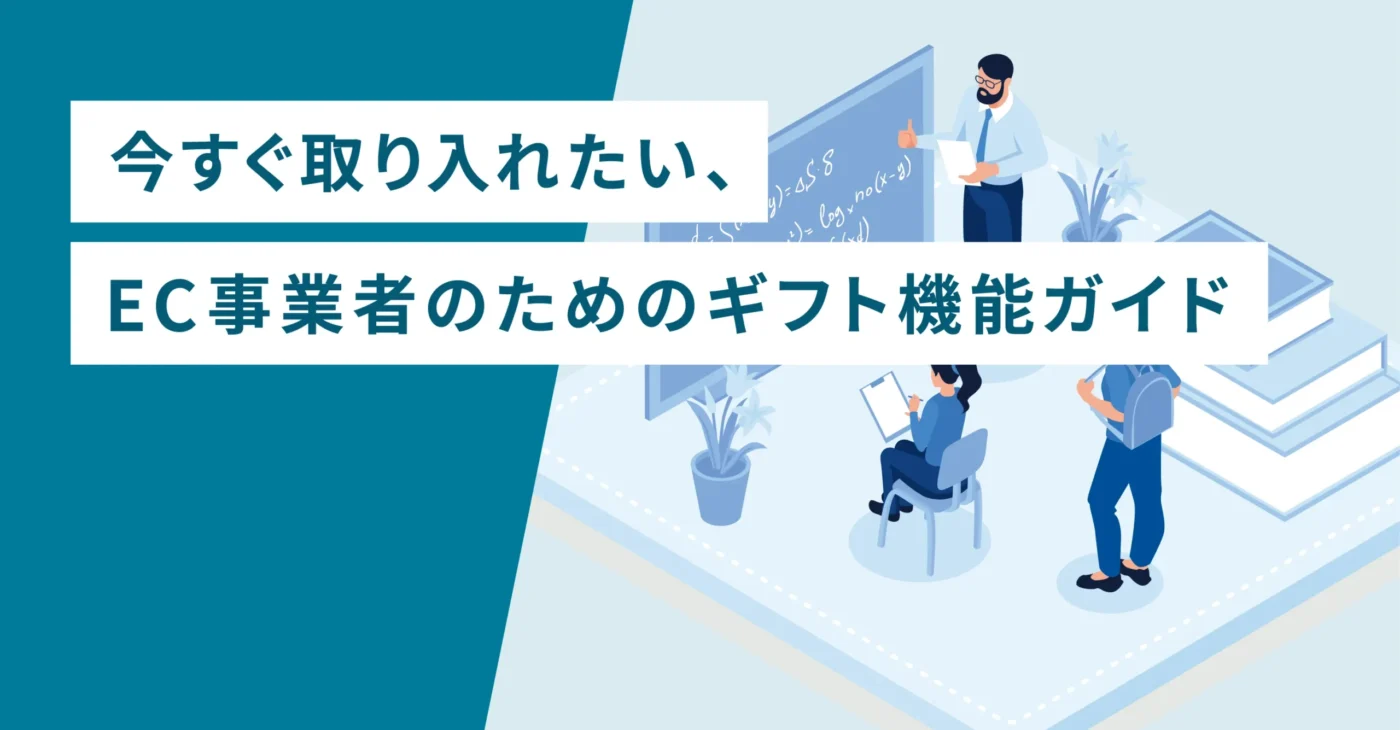
ネットショップの売上を伸ばすならギフト対応がカギ。ラッピングやeギフト導入で客単価もUP
ネットショップを運営していると、「商品は買われているのに、なぜかリピートや客単価が伸びない」という悩みに直面することがあります。
そんな時に見落とされがちなのが「ギフト対応」の有無です。
国内のギフト市場は拡大を続けています。矢野経済研究所によると、国内ギフト市場規模は2022年に約10.5兆円、2023年は10.8兆円と成長傾向にあります。
出典:株式会社矢野経済研究所「2024年のギフト市場規模は前年比102.7%の11兆1,880億円の見込
~より親しい間柄において、コミュニケーション手段として高まる「ギフト」の存在価値~」
また、自家消費とギフト購入には明確な違いがあります。自分用では「訳あり」「大容量」などのコスパ重視が多いのに対し、ギフトでは「見た目」や「品質」を重視し、平均単価が1.3〜1.5倍高くなる傾向があります。
つまり、ギフト対応を導入することは「新しい顧客層を取り込む」だけでなく「売上単価を伸ばす」ことにも直結する重要な施策なのです。
ギフト対応は「ページ作り」がカギ
ギフトと聞くと、かつてはお中元やお歳暮などフォーマルな贈答品を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし最近は「友人への誕生日プレゼント」「同僚へのちょっとしたお礼」「推し活の差し入れ」など、日常的なカジュアルギフト需要が拡大しています。
自社にギフト専用商品がなくても心配はいりません。
「ラッピング可能」「熨斗対応可」などの選択肢を用意するだけでも、“贈り物に使えるネットショップ”として選ばれやすくなるのです。
逆に、ラッピングや熨斗の選択肢がなければ「ここでは買えない」と離脱されることも少なくありません。ギフト対応は単なる付加価値ではなく、顧客の購入判断を左右する導線となります。
ギフト対応は「ページ作り」がカギ
せっかくギフト対応を用意しても、それを伝えられなければ意味がありません。
多くのネットショップでは、ラッピングやメッセージカードの案内が分かりづらく、ユーザーが「対応していない」と勘違いしてしまうケースが見られます。
ギフト対応の肝は「ページ作り」です。
- ・ラッピング対応の有無を明確に表示
- ・包装や熨斗の写真を掲載し、選ぶイメージを具体的に持たせる
- ・メッセージカードのサンプル文や選択肢を提示する
- ・納品書や送り主名の扱いを事前に案内し、安心感を与える
特に「ギフトを贈り慣れていない人」にとっては、ページが親切かどうかが購入判断の決め手になります。ギフト対応は「できます」と書くだけでは不十分であり、“どんなふうに贈れるのか”を見せることが、信頼につながります。
導入すべきギフトページの要素
ギフト対応を整える上で最も重要なのは「専用ページをどう作るか」です。
ただラッピングサービスを提供しているだけでは、利用者には伝わりません。特にネットショップでは、実店舗のように手に取って確認することができないため、ページ内の説明や写真がそのまま「安心材料」となります。
どのような包装や熨斗が用意されているのか、どんな雰囲気で贈れるのかを明示して初めて、ユーザーは「ここなら安心して任せられる」と判断できます。
ここでは、ギフトページに盛り込むべき要素を具体的に整理します。
対応可能なラッピングや熨斗の種類
ギフトページでまず必要なのは、「どんなラッピングや熨斗が選べるのか」を明確に提示することです。
- 包装紙の種類:シンプル・華やか・和柄など複数用意し、写真つきで並べる
- 熨斗の種類:紅白蝶結び(一般的なお祝い)、結び切り(結婚祝い・快気祝い)、黄白(弔事用)など、用途ごとに説明を添える
- 選び方のガイド:「出産祝いには蝶結び」「結婚祝いは結び切り」など、初心者でも迷わない説明を加える
熨斗や包装の知識がなくても選べるような“ガイドとしての要素”が信頼感を高めます。
ラッピングの実物写真やサイズ感
ラッピング対応をアピールする上で、視覚的に分かりやすい写真は欠かせません。
- ・実際の商品を包んだ見本写真を掲載する
- ・袋や箱の大きさが分かるよう、サイズ比較を明記する
- ・高級感のある紙/シンプルなエコ包装の雰囲気を並べて紹介する
ネットショップの利用者は「想像と違ったらどうしよう」という不安を抱きやすいため、完成イメージが伝わる写真が安心感を与えます。
メッセージカードのサンプル文
贈り物には「言葉」が添えられると一層気持ちが伝わります。
ただし、自由入力欄だけでは「何を書いたらいいか分からない」と悩む人も少なくありません。
- ・「お誕生日おめでとうございます」「いつもありがとうございます」などの定型文をいくつか用意
- ・季節やイベントに合わせた文例(母の日・クリスマスなど)も選べるように
- ・自由入力も可能にして柔軟性を担保
「文例があるから安心して選べる」「自分の言葉も入れられる」この両立が大切です。
納品書や送り主名の扱い(安心感)
ギフトで最も多いトラブルのひとつが「受け取った人に請求が伝わってしまう」「誰から贈られたのか分からない」という問題です。
- ・金額の入った納品書は同封しない設定を案内する
- ・送り主の名前を伝票やメッセージカードに必ず記載する
- ・匿名にならないよう、システムで制御する
こうした配慮があるだけで「安心して利用できるショップ」という印象を持たれやすくなります。
季節限定や用途別のギフト提案(母の日/結婚祝いなど)
ギフト需要は季節やライフイベントと密接に関わっています。
そのため、ギフトページでシーズンごとの特集や提案を設けると効果的です。
- ・母の日/父の日/クリスマス/バレンタインなどの季節イベント
- ・結婚祝い/出産祝い/快気祝い/新築祝いなどライフイベントごとの提案
- ・価格帯別・利用シーン別で商品をまとめて紹介
「選ぶのが大変」というユーザーにとって、おすすめの切り口を提示すること自体が価値になります。
ギフトページは単なるサービス案内ではなく、「安心して贈れるかどうか」をユーザーに判断してもらう場です。
実物写真・用途別の説明・トラブル防止の工夫を丁寧に盛り込むことで、ギフト初心者でも安心して購入できるネットショップに変わります。
導入すべき機能の具体例
ギフトページを整えるだけでは不十分です。
実際に注文を受け、利用者にとってストレスのない購入体験を実現するためには、ネットショップ側の機能も大きな役割を果たします。
ギフトは「贈る人」と「受け取る人」が別であるため、通常の買い物以上に細やかな配慮が必要です。
ここでは、ネットショップに導入しておきたい代表的な機能を具体的に紹介します。
ラッピング選択肢
ラッピングは複数のデザインを用意し、注文時に選べるようにしておくのが基本です。さらに、選んだデザインをプレビューで確認できれば、利用者は安心して決断できます。季節限定やエコ包装といった選択肢を追加すると、より幅広いニーズに応えられます。
メッセージカード/熨斗/掛紙
熨斗やカードは用途別にテンプレートを用意するのが親切です。たとえば「紅白蝶結び」「結び切り」といった定番を選べるようにしつつ、自由記入欄も残せば柔軟性を保てます。仕上がりイメージを最終確認できるフローを入れておくと、誤記やトラブルも防げます。
複数配送先の指定
ギフト購入では「親戚・友人へまとめて贈りたい」「取引先へ一斉に届けたい」といったケースが少なくありません。通常の注文フローでは宛先ごとに繰り返し購入する必要があり、ユーザーの大きな負担になります。
1回の注文で複数の配送先を指定できれば、その手間を解消できるだけでなく、法人需要や年末年始の贈答品需要といった大口注文も取り込みやすくなります。結果的に、ショップへの信頼感やリピート利用にもつながる機能です。
eギフト(ソーシャルギフト)
近年注目されているのが「eギフト」です。相手の住所を知らなくても、LINEやメールでURLを送るだけで贈れる仕組みで、特にSNS世代のカジュアルギフトとして定着しつつあります。
「ちょっとしたお礼」「誕生日のサプライズ」「SNSキャンペーンの景品」など、これまで機会損失になっていたライトギフト需要を取り込める点が大きな魅力です。ネットショップがこの仕組みに対応できれば、新しい顧客層の開拓につながる可能性があります。
ギフト対応は、単なる包装やカード提供にとどまりません。
ラッピングの多様性、熨斗やカードの案内、複数配送先やeギフトといった機能は、「使いやすさ」と「安心感」を同時に提供する仕組みです。
これらを整えることで、ネットショップは贈り物をする場所として選ばれる存在へと進化します。
ギフト対応時に気をつけるべき運用設計
ギフト対応をネットショップに導入する際、華やかな見せ方や機能に目が行きがちですが、実際の運用でトラブルが起きると、せっかくのサービスがかえって不満のもとになります。特にギフトは「贈る人」と「受け取る人」の二者が関わるため、通常の購入以上に細やかな配慮が求められます。ここでは、現場でよく起こりがちな落とし穴と、その回避策について整理してみましょう。
ラッピング料金の明確化
ラッピングを無料で提供するか、有料にするかはショップごとに異なります。しかし、どちらにしても重要なのは「料金の内訳をわかりやすく提示すること」です。注文後に「ラッピング代が加算されていた」となってしまうと、不信感につながります。料金が発生する場合は、商品ページやカート画面の段階でしっかり金額を表示し、利用者の納得感を得ることが欠かせません。
支払い方法の設定
ギフト対応でもっとも注意したいのが代引きの扱いです。通常の購入では便利な代金引換も、ギフトでは「受け取った人が代金を請求される」というトラブルを招きかねません。そのため、注文フォームで配送先と支払い方法の組み合わせを制御し、ギフト配送の場合には代引きを選べないように設定することが大切です。小さな工夫ですが、これだけでクレームやキャンセルのリスクを大幅に減らせます。
配送にまつわるトラブル対策
ギフトは記念日やイベントに合わせて届けることが多いため、納期厳守が強く求められます。「間に合わなかった」だけで利用者の満足度は一気に下がり、再購入の可能性も低くなります。
また、配送伝票に記載される名前にも注意が必要です。送り主の名前が正しく表示されなかったり、省略されてしまうと、受け取った人が「誰から送られたのか分からない」状態に陥ってしまいます。これはギフトにおいては致命的な問題です。
熨斗の書き方・確認フロー
熨斗や掛紙を取り扱う場合、入力内容の誤りがトラブルに直結します。たとえば贈り先の名前が間違っていると、失礼になるばかりか返品や再送のコストも発生します。そこで役立つのが、自動入力機能やプレビュー確認画面です。注文者が実際の仕上がりを見ながら最終チェックできれば、ショップ側の負担も軽減されます。
送り主不明のトラブル回避
意外に多いのが「受け取ったけれど、誰から送られたか分からない」というケースです。これは熨斗やカードに送り主名がなかったり、納品書が匿名だったりすると起こりがちです。必ず注文者名をどこかに明記する仕様を整えておくことで、このような不安を解消できます。
ギフト対応は「見せ方」以上に「運用設計」が成否を分けます。料金の扱い、支払い方法、配送の細部まで意識した上で仕組みを作り込むことで、トラブルを未然に防ぎ、顧客に安心して利用してもらえるネットショップへと成長させることができるのです。
導入・運用のステップ
ギフト対応は「資材を揃えてページを作る」だけでは十分ではありません。実際には、注文から梱包、出荷までの一連のフローに組み込まなければならず、現場が混乱しない仕組みづくりが欠かせません。特に小規模でネットショップを運営している場合、担当者1人が複数の業務を兼務していることも多く、準備不足だとすぐにオペレーションが破綻してしまいます。ここでは、導入から運用までをスムーズに進めるための基本ステップを順を追って整理します。
1. ラッピング資材の検討
最初に取り掛かるべきは、包装紙・袋・熨斗・メッセージカードといった資材の準備です。
最低限のラインナップから始めても構いませんが、「誰にでも使いやすいシンプルなデザイン」「シーズン限定デザイン」を揃えると、利用者の満足度は高まります。資材のコストは意外と嵩むため、無料で提供するものと有料オプションにするものをあらかじめ用意しておきましょう。
2. 商品ページの修正
資材を揃えたら、ギフト対応の存在をユーザーに伝えることが次のステップです。
商品ページには「ギフト対応可能」マークを付けたり、画像の下に「ラッピング可」と記載するだけでも印象は大きく変わります。専用ページだけに情報をまとめるのではなく、ユーザーが購入検討の場面で気づけるように表示を分散させることが大切です。
3. 注文画面の改修
実際にギフトを選んでもらう段階では、注文フォームに選択肢を設置する必要があります。
「ラッピング希望」チェックボックスや熨斗の種類選択、メッセージ入力欄などをわかりやすく配置し、入力ミスを防ぐための確認画面も用意しましょう。ここでの体験がスムーズであればあるほど、ギフト購入がリピートにつながります。
4. 社内フローの整備
ギフト対応を導入すると、通常の梱包とは異なる作業が発生します。スタッフが迷わず対応できるように、ラッピング手順書や検品チェックリストを用意しておきましょう。
「どの商品がギフト対象なのか」「どの包装紙を使うのか」などをマニュアル化しておけば、繁忙期でも安定した品質を保つことができます。
5. 支払い方法の制御
最後に、運用面で特に重要なのが支払い方法です。前章でも触れましたが、ギフト配送では代引きがトラブルのもとになるため、システム側で制御するのが鉄則です。また、クレジットカード・コンビニ払い・後払いなど、受け取り人が負担しない決済手段を中心に整備することが望ましいでしょう。
ギフト対応の導入は「商品にリボンをつける」だけの簡単な施策ではありません。資材の調達からページの修正、注文フォームの設計、スタッフ教育、決済設定まで、実際の運用を見据えた準備が欠かせません。
最初は小さな範囲から始めても構いませんが、ステップを踏んで整備していけば、ネットショップ全体の信頼性を高め、ギフト需要を確実に取り込める体制へと成長できます。
ギフト対応は「売上UP+離脱防止」の両輪
ギフト対応は、単なるサービス拡張ではなく「単価アップ」と「離脱防止」の両方につながる重要な取り組みです。ラッピングや熨斗、納品書や送り主情報の扱い、支払い方法の制御まで丁寧に整えることで、ユーザーは安心して「ギフトに使えるショップ」としてあなたのネットショップを選ぶようになります。
しかも、大掛かりな投資から始める必要はありません。まずは専用ページを作り、基本的なラッピングやメッセージカード機能を用意するだけでも効果は十分。こうした一歩が、ショップ全体の信頼や売上単価の向上につながります。
そして、こうした仕組みをスムーズに導入できるのがネットショップ構築システムのEストアーショップサーブです。ラッピング・熨斗の選択肢やギフトページの作成、複数配送先やeギフトといった拡張機能まで柔軟に対応できるので、初めてでも安心。もし「自分のネットショップでもギフト対応を始めたい」と感じたら、Eストアーショップサーブの機能をチェックしてみてください。あなたのショップを“ギフトに選ばれるショップ”へと進化させる力強い後押しになるはずです。