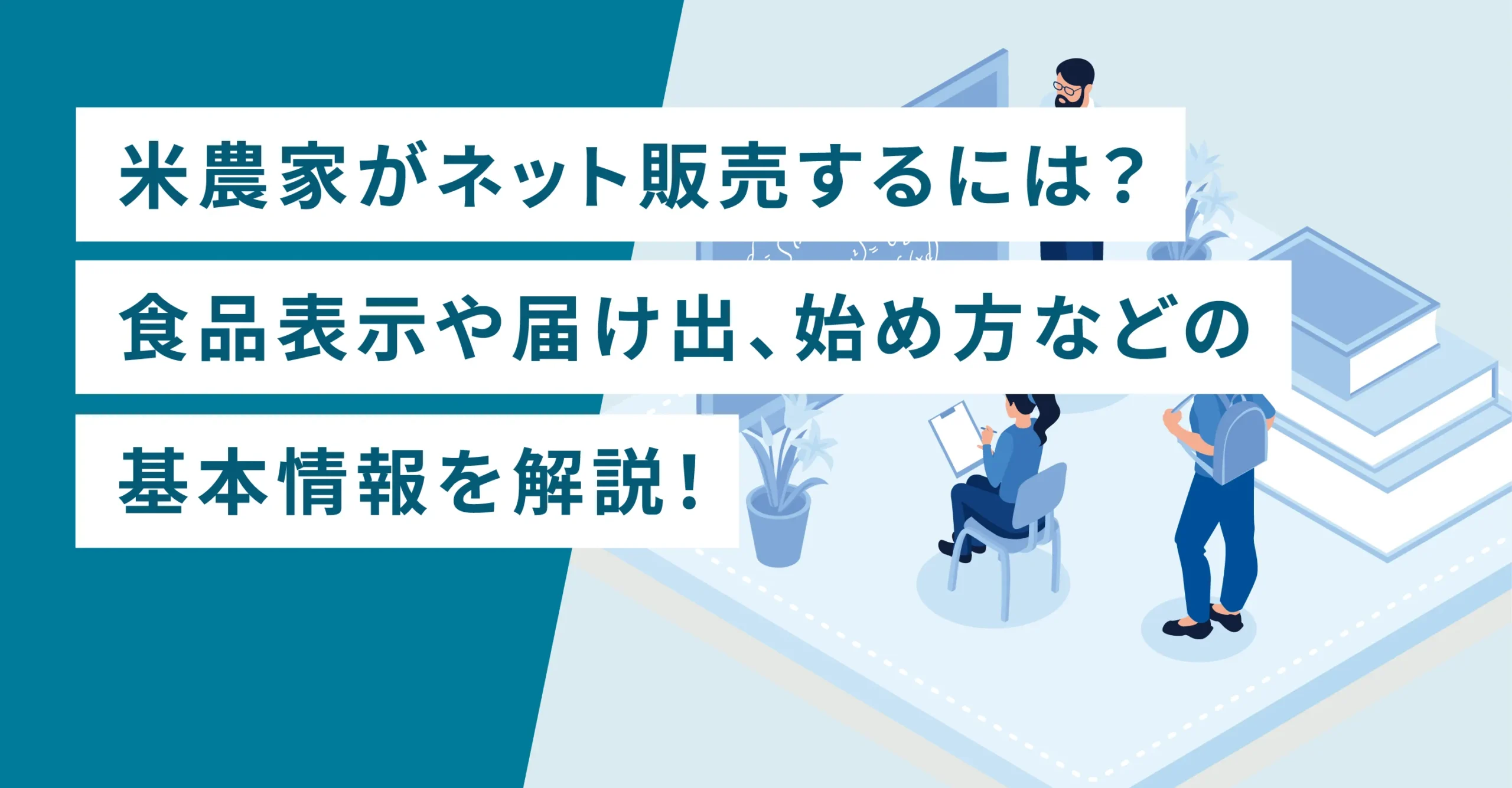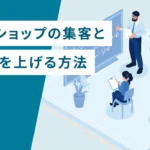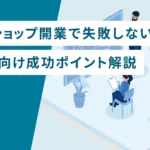米農家のためのネット販売入門。 届出、食品表示、ネットショップ選びを解説
近年の米価高騰を背景に、多くの米農家が経営の厳しさを実感し、直接販売への意識に変化が生じています。
株式会社ビビッドガーデン(「食べチョク」運営)が2025年5月に実施した調査では、約45.1%の生産者が「直販を増やす予定」と回答し、そのうち約66%が「産直通販サイト(例:食べチョク)などへの販売を強化するつもり」と答えています。
出典:株式会社ビビッドガーデン「令和7年産米に関する意識調査」(2025年5月発表)PR TIMES プレスリリース
背景には、物価上昇や肥料・燃料費の高騰といった経営環境の急変があり、JAや卸売中心の従来ルートでは価格決定権が小さく、収益性の低さが課題となっています。こうした現状が、農家自身によるネット販売や自社ECへの関心を高める大きな要因となっているようです。
この記事では、米農家さんが初めてネット販売に挑戦する際に知っておきたいポイントを、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。法律や手続き、販売方法まで、疑問を解消し安心して一歩を踏み出せるようサポートします。

まず知っておきたい!ネットで米を売るときの基本ルール
お米をネットで販売する際には、いくつか知っておくべき国のルールがあります。これらを理解しておくことで、安心して販売を始められます。
農政局への届出(年間20トン以上のみ)
お米を販売するにあたり、すべての農家さんが農政局に届け出る必要はありません。年間20トン以上のお米を販売する場合にのみ、「米穀の出荷または販売の事業を行う者」として農政局に届け出る必要があります。年間20トン未満の販売であれば、この届出は不要です。
食品表示法:品種・産地などの表示義務
お客様が安心して購入できるように、販売するお米には食品表示法に基づいた表示が義務付けられています。具体的には、以下の項目を正確に表示する必要があります。
- 名称:精米、玄米など
- 産地:都道府県名、市町村名、またはそれらを特定できる地域名
- 品種:単一原料米の場合は品種名(例:コシヒカリ)、複数原料米の場合はその旨
- 内容量:正確な重さ
- 精米年月日または調製年月日
- 販売者情報:氏名または名称、住所、電話番号
これらの情報を記載した食品表示ラベルを準備しましょう。
計量法:正確な重さの表示とスケールの基準
お米の販売においては、計量法に基づき、表示した内容量と実際の重さが合っていることが求められます。そのため、お米の計量に使うスケール(はかり)は、正確な計測ができる家庭用ではない、取引・証明用のものを使用する必要があります。購入する際は「検定付」や「取引証明用」と表示されたものを選びましょう。
加工する場合(炊飯・もち等)の営業許可
収穫したお米をそのまま販売するのではなく、炊飯米やもち、米粉パンなどに加工して販売する場合は、別途、保健所の営業許可が必要になります。これは、加工食品を製造・販売する際に衛生管理が求められるためです。加工品の販売を検討している場合は、事前に管轄の保健所に相談し、必要な許可や施設基準について確認しましょう。
ネット販売のメリット
「ネット販売って大変そう」と感じるかもしれませんが、実は農家さんにとって多くのメリットがあります。
卸より高く売れる(直接販売で利益率UP)
これまでの流通経路では、卸業者や小売店を介するため、その分手数料が発生し、農家さんの手元に残る利益が少なくなってしまいがちでした。しかし、ネット販売で直接お客様に届けることで、中間のマージンを削減でき、卸に比べて高い価格でお米を販売できます。これにより、利益率を大きく向上させることが可能です。
お客様の声がダイレクトに届く
ネット販売では、お客様からのレビューやメッセージが直接届きます。これにより、「このお米は粘りが強くて美味しい」「炊き上がりの香りが良い」といった生の声を直接聞くことができます。お客様からの声は、今後の栽培の参考にしたり、新しい商品開発のヒントになったり、農業経営にとって貴重な財産となるでしょう。
リピーターがつきやすい(定期購入のニーズあり)
一度気に入ってくれたお客様は、リピーターになる可能性が高いです。特に、お米は毎日の食卓に欠かせないものなので、定期的に購入してくれるお客様が増えることで、安定した売上につながります。中には「毎月〇kg送ってほしい」といった定期購入のニーズもあり、安定した販路を築きやすいのが特徴です。
自分のペースで続けられる(副業や家族経営にも)
ネット販売は、時間や場所に縛られずにできるため、自身の都合に合わせて作業を進められます。例えば、農作業の合間や、家族経営の中で役割分担をしながら取り組むことも可能です。無理なく自分のペースで続けられるため、本業の傍らで新たな販路を築きたい方や、家族で協力して農業に取り組む方にも適しています。
ネット販売のデメリット
メリットがある一方で、ネット販売には注意すべき点もあります。
出荷や梱包に手間がかかる
ネット販売では、注文が入るたびに お米を計量 → 袋詰め → 梱包 → 発送する 作業が発生します。大量の注文が入った場合、これらの作業にかなりの時間と労力がかかる可能性があります。特に、精米から発送までを自分で行う場合は、効率的な作業フローを考える必要があります。
最初は売れなくて不安になることも
ネット販売を始めたばかりの頃は、なかなか注文が入らず、「本当に売れるのだろうか」と不安になることもあるかもしれません。競合も多いため、すぐに大きな売上につながるわけではないことを理解しておく必要があります。焦らず、地道に商品情報を充実させたり、SNSなどで情報発信を続けたりすることが大切です。
法規制のチェックや表示ミスに注意が必要
前述の通り、お米の販売には食品表示法や計量法といった国のルールが関わってきます。これらの法規制をきちんと理解し、表示に誤りがないか常にチェックする必要があります。もし表示に不備があった場合、お客様からの信頼を失うだけでなく、法的な問題に発展する可能性もゼロではありません。
ネット販売の3つの方法と特徴
実際にネットでお米を販売する方法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を理解し、自身に合った方法を選びましょう。
フリマアプリ(メルカリ等)
フリマアプリは、手軽に個人間の売買ができるプラットフォームです。スマートフォンの操作だけで簡単に出品できるため、ネット販売初心者の方には比較的挑戦しやすいものです。
しかし、注意点があります。2025年以降、お米の転売に関する規制が強化される動きがあります。個人が不特定多数に営利目的でお米を販売する場合、これまでのようなフリマアプリでの販売が難しくなる可能性があります。現時点では詳細が未定ですが、今後も情報収集が必要です。基本的には、個人での少量販売や自家消費の余剰分を譲る目的で利用されることが多く、本格的なビジネス展開には向かないかもしれません。
ECモール(楽天・Amazon・食べチョクなど)
楽天やAmazon、食べチョクのようなECモールは、多くのお客様が訪れる巨大なショッピングサイトです。ここにショップを出店することで、自力で集客する必要がなく、最初から多くのお客様に商品を見てもらえるという大きなメリットがあります。
一方で、モールごとに決められた出店手数料や販売手数料が発生します。また、モールの定める複雑なルールや規約に従う必要があり、自由なショップ運営が難しいと感じることもあるでしょう。集客力は魅力的ですが、コストや制約についても考慮が必要です。
自社EC
自社ECは、自分自身でゼロから作り上げるオンラインショップです。ショップのデザインや商品の見せ方、価格設定など、すべてを自由な発想で決めることができます。 ECモールのような手数料に縛られることも少なく、長期的に見れば最も利益率が高い販売方法となる可能性があります。
ただし、サイトの構築や商品の登録、集客活動など、すべてを自分で行う必要があります。最初のうちは手間がかかるかもしれませんが、ブランドや商品の世界観を存分に表現でき、お客様との深い関係を築きやすいという点で、最も大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。
ステップで解説|ネット販売の始め方(精米販売の例)
ここでは、精米をネットで販売する際の具体的なステップをご紹介します。
1. 農政局に確認(20トン以上の販売は届出が必要)
まずは、年間のお米の販売量を確認しましょう。前述の通り、年間20トン以上を販売する場合のみ、農政局への届出が必要です。初めての販売で少量から始める場合は、この届出は不要なことが多いでしょう。念のため、管轄の農政局に確認しておくと安心です。
2. 食品表示ラベルの準備
販売するお米には、食品表示法に基づいたラベルの貼付が必須です。表示すべき項目(名称、産地、品種、内容量、精米年月日または調製年月日、販売者情報)を正確に記載したラベルを作成しましょう。手書きでも構いませんが、見た目を整えるためにも印刷することをおすすめします。
3. 出店先を決める(自社EC or モール)
フリマアプリ、ECモール、自社ECの3つの方法の中から、目的に合った出店先を選びましょう。
・手軽に始めたい → ECモール
・長期的に安定した経営を目指すなら → 自社EC
それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、販売戦略に合った方法を選択してください。
4. 商品ページを作る(品種・味・産地のこだわりを書く)
お客様が商品を購入する際に最も参考にするのが、商品ページです。お米の品種名や味の特徴だけでなく、どんな場所で、どんな思いで作っているのかを詳しく記載しましょう。写真も重要です。美しい田園風景や、お米の粒がわかるような鮮明な写真を掲載することで、お客様に商品の魅力を伝えることができます。「こだわり」を存分にアピールしましょう。
5. 注文が入ったら梱包して出荷
お客様から注文が入ったら、いよいよ発送作業です。計量法に基づき、正確な重さでお米を袋詰めし、破損がないように丁寧に梱包します。配送業者を選び、指定された方法で出荷しましょう。お客様に気持ちよく受け取ってもらえるよう、丁寧な対応を心がけてください。
よくある質問
Q. 精米して売るだけなら保健所の許可はいらない?
A. はい、基本的に精米してそのまま販売する場合は、保健所の営業許可は不要です。
保健所の営業許可は、食品を加工する際に衛生管理の観点から必要となるものです。お米を精米する作業は「加工」とはみなされないため、特別な許可は必要ありません。ただし、精米したお米を使っておにぎりやもちなど、別の加工食品を製造・販売する場合は、別途保健所の営業許可が必要になりますのでご注意ください。
Q. 品種名を表示するには登録が必要?
A. いいえ、品種名を表示するために、特別な登録は必要ありません。
ただし、表示する品種が「〇〇(品種名)100%」であることを明確にするために、適切な管理と品質確認を行う必要があります。もし複数の品種を混ぜて販売する場合は、「複数原料米」と表示することが食品表示法で義務付けられています。正確な情報を表示することが大切です。
Q. お米はどのような配送方法で送れる?
A. ゆうパックをはじめ、ヤマト運輸や佐川急便など、主要な宅配便サービスでお米を送ることが可能です。
各社ともに重さに応じた料金設定があり、クール便などのオプションサービスも利用できます。ご自身の発送量や料金、サービス内容を比較検討し、最適な配送業者を選びましょう。特に、契約運賃を利用することで、送料を抑えられる場合もありますので、大量に発送する予定がある場合は、各社に相談してみることをおすすめします。
“売る力”は農家の未来を守る
これまで「作る」ことに専念してきた農家さんにとって、「売る」ことは新しい挑戦かもしれません。しかし、ネット販売は、丹精込めて作ったお米を、より多くのお客様に届けるための素晴らしい方法です。そして、これは単なる売り方の多様化にとどまらず、市場の変化に対応し、農業経営を未来へとつなぐための「売る力」を育むことにもつながります。
「お米は作れるけど、売るのは難しい」と感じる必要はありません。法律や手続き、ネット販売のノウハウも、一つずつ理解していけば、決して難しいことではありません。
しかし、「やっぱり一人でネットショップを始めるのは不安だな」「専門的な知識がないと難しいのでは?」と感じたなら、ぜひEストアーショップサーブにご相談ください。
Eストアーショップサーブは、26年間の豊富な実績をもとに、多くのEC事業者をサポートしてきました。特に、食品を扱うEC事業者様が多く、これまで培ってきた経験から、食品販売に特化した機能や、販売促進に関するきめ細やかなサポートを提供しています。
ECに初めて挑戦する方でも、ネットショップの立ち上げから運用まで、担当者が手厚くサポートします。難しい専門知識は不要です。“売る力”を育み、成功へと導くために、私たちが全力で伴走します。
まずは、お気軽にお問い合わせください。